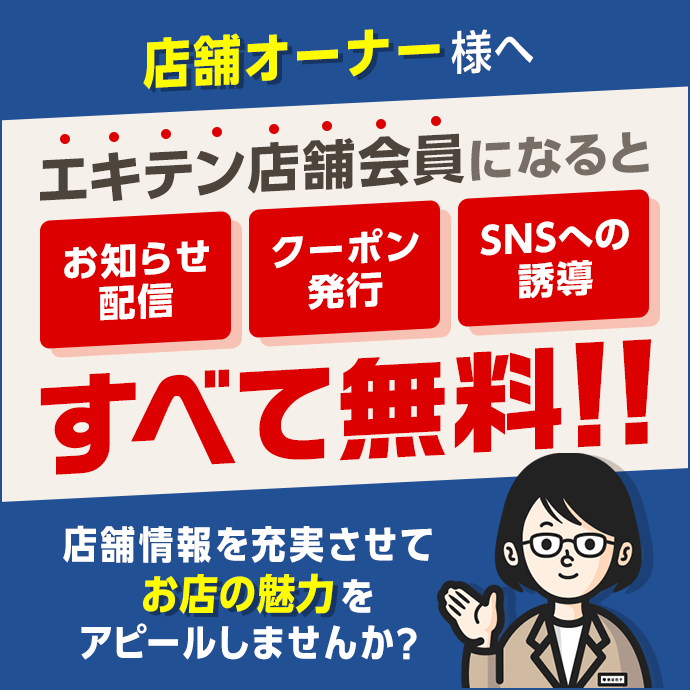口コミ
四国八十八ヶ所巡礼の旅で参拝しました。四国八十八ヶ所霊場の第二十九番札所です。天平時代、聖武天皇の勅願により行基が創建した官寺です。風格ある仁王門をくぐり杉木立の参道を通り本堂ヘ向かいます。重要文化財に指定されている本堂は柿葺き、寄棟造りとなっていて風情があります。境内は綺麗に整備されていて苔が美しい庭園があり、静かで凛とした雰囲気が漂うお寺でした。
四国八十八ヶ所霊場の第二十九番札所です。聖武天皇が発した「国分寺建立の詔」により全国に建立された国分寺(金光明四天王護国之寺)の一つで、天平13年(741年)に行基が千手観世音菩薩を刻み本尊として安置し開創したと伝わる古い歴を持つ寺院です。山門をくぐって進んでいくと右側に鐘楼が、左手に開山堂が、正面奥に本堂が建ち、その左に大師堂が鎮座されています。本堂は、柿葺き、寄棟造りで外観は天平様式を伝え、内部の海老紅梁は土佐最古といわれるもので国の重要文化財に指定されています。境内は、全域が国の史蹟に指定され、杉苔が美しい庭園で「土佐の苔寺」ともいわれています。
南国市にあるお寺です。
奈良時代の天平時代に当時土佐で
一番文化的に進んでいたこの地に
できたみたいです。
近くに昔の県庁的な国司もあったみたいです。
2018年5月に行った時は、お遍路さんも
いっぱいいたみたいで写真も撮ってます。
この時は、近くの岡豊城に観光に行って
頂上から場所を確認して国分寺に行きました。
なかなかお寺として風水的にも
よくできていると思います。
歴史的遺産です。
本堂(金堂)は国の重要文化財
- 投稿日
四国八十八ヶ所巡礼の旅で参拝しました。高知自動車道の“南国IC”から車で5分ぐらいの所にあります。第二十八番札所大日寺からだと車で20分足らずかかります。
聖武天皇が発した“国分寺建立の詔”により全国に建立された国分寺の一つです。
境内全域が国の史跡に指定され杉苔が美しいことから“土佐の苔寺”とも言われているそうです。
山門を進むと右手に鐘楼が、左手に開山堂が、正面奥に本堂と大師堂があります。国の重要文化財に指定されている本堂(金堂)はこけら葺き、寄棟造りの建物で風格がある素晴らしい造りです。
境内には“酒断(さけだち)地蔵尊”があって、断酒を願うとご利益が叶うということで、多くの参拝者が願い事をするそうです。酒断ちにご利益があると言うお守りが販売されています。
無料の駐車場があります。
7月21日に日帰りで四国遍路の続きを回ってきました。愛南町から高知市への所要時間は松山市に行くのとほぼ同じなので、この辺まで来れば日帰りでも十分時間が確保できます。
今回は二十九番国分寺からスタートです。高知市内から国道195号を東へ進み、国道32号との交差点を左折します。あとは看板に従い進むと到着します。大型バス用の駐車場は目立つのですが、一般車用の駐車場は細くなっている道を右に入ったところにあるので気づきにくいかもしれません。
国分寺は当時の国ごとに同名のお寺が建立されているので、「土佐国分寺」と呼び区別することもあるようです。
仁王門をくぐると、正面にこけら葺き(かやぶきのようなもの)の屋根が特徴の本堂が見える…はずだったのですが、改修工事のため、本堂は参拝できるスペースが確保されているだけで他の部分は工事用の壁で囲まれていました。残念。
本堂の左には大師堂があります。また、大師堂の近くには「酒断ち地蔵」というお地蔵様がまつられています。もとは「ひとこと地蔵」と呼ばれ、願いを一つかなえてくれるというご利益があったそうですが、夫の酒をやめさせて欲しいと頼んだ女性の願いがかなったことから呼び名が変わって親しまれてきたそうです。私は下戸なので、酒断ちできた人の分飲めるようにしてほしいとお願いしてきました。
納経所は本堂手前を右に入ったところにあります。庭園や宝物館のような建物もあるようで、別途料金を払えば見学可能とのことでした。納経所の横から駐車場前に出る裏口もあるようですが、マナーとして仁王門まで戻り一礼して後にしました。